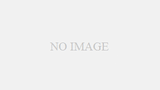最近、未経験から農業に転身する人々が増えています。しかし、ひとりで0から農業を立ち上げることは、とてもハードルが高く簡単ではありません。それなら 「すでにうまくいっているやり方を学んだほうが早い」と、コスパの高い農家への道をおすすめするのが、今回お話をお伺いした内山貴博さんと奥様のエリカさんです。デコポン発祥の地・熊本県で、本物の味を追い求める農家を営む経営者です。家業の果樹園を引き継ぎながら、地域社会に貢献するために積極的に活動されています。
「こんなことがやりたい」思いをどんどん叶えていく姿勢は、これから農家を目指す人だけではなく、独立・起業に興味がある人にも、成功するヒントになるかもしれません。
熊本で果樹園を営んでおります、うちやま果樹園代表の内山貴博と申します。
20歳のころから家業の果樹園に従事し、今は*デコポンやシャインマスカットづくりをしています。妻、子ども3人の5人家族です。
*熊本果実連が所有する登録商標。日本園芸農業協同組合連合会(日園連)を通じて出荷されたシラヌイ等のうち、糖度13度以上、酸度1度以下を満たしたもの。
<うちやま果樹園のデコポンと内山さんご家族>
もともと父方は養豚業、母方は地域でも一番小さい果樹園で農業を営む一家でした。私は母方の果樹園を手伝うようになりました。継ぐ決意をしたわけではありません。
20歳ころから手伝っていて、果樹園の土地をだんだんと広げて規模を大きくしていたのでそのまま引き継ぎました。手伝い始めたころ、まだ果樹園は小さく、収穫量も十分ではありませんでした。
生活安定のため、朝から日中までは果樹園で働きつつ、夕方はアルバイトをしていました。そういった生活が10年くらいは続いたでしょうか。
親子で意見の相違があり、果樹園を運営するのが大変でした。
私は効率よく果物を作れるように、新しいやり方を考えるのですが、親たちは「今まで通りのやり方を守りたいから」と、意見を受け入れてくれず説得が難しかったです。
多くの果樹園でも、同じ問題にぶつかるようです。
ほかの果樹園では、意見の相違から親子で一緒に経営できなくなり、別々の果樹園の運営になることが多いのですが、私たちは話し合って意見をすり合わせていきました。
各自が譲れないポイントはお互い口出しをせず、少しずつ一緒に運営するための取扱説明書を完成させていきましたね。
8年ほど前に代替わりをし、果樹園経営者としてはかなり若い30代前半でうちやま果樹園の代表になりました。
妻の実家の畑が近くにあり、跡継ぎがいなかったので、私に任せていただくことになりました。
このころから少しずつ畑の土地を広げていき、今では4ヘクタールの畑(東京ドーム1個分ほど)を管理しています。
最初、デコポンの栽培はほんの少量でした。インゲン豆やミカンを主に栽培していましたが、利益の見込みが薄いので、高単価で出荷できるデコポンやブドウに力を入れるようにしました。
デコポンに限らず果物は、木を育てなければならないので時間がかかります。
目先のことを考えるならば他の野菜を育てる方が早いかもしれませんが、長期的に果樹園の将来を考えデコポンやブドウの栽培に特化していきました。
味にこだわりを持っています。そのためには有機肥料が大事なのですが、たまたま両親が前から有機肥料を使っていました。
*うちやま果樹園でとれるデコポンがおいしいと言われ、後からなぜか考えてみたら土が違うことがわかりました。
ほかの果樹園では、作業の効率化のために除草剤を使いますが、うちやま果樹園では除草剤を使わずに草木を手で刈り取っています。
そのため土の中に多くの微生物がおり、デコポンの味に影響して味の濃いデコポンができあがります。
*「うちやま果樹園」さんでは、農業従事者ではない一般の方にもこだわりポイントがわかりやすいように、Instagramを使って、収穫の様子や加工商品、果物の様子を発信しています。
うちやま果樹園【こだわりの味を追求する農家👩🌾】(@uchiyamakajuen)がシェアした投稿
ブドウ栽培のために行っている調査なのですが、どの時期にどの肥料がより多く吸収されているかを調べています。
いままでは経験と勘を頼りに栽培してきたのですが、どの養分が吸収されやすいのかを数値化して再現性を見つけ、より効率的においしい果物を栽培できるようにするため、検査を始めました。
ひとりではできないので、長野県の果樹園を経営する方々と共同で行っています。
<うちやま果樹園代表 内山貴博さん>
「味が濃い」ことが特徴です。土にこだわって作っているので果物の細胞自体が強くなります。
熊本は台風などの自然災害も多いのですが、果物の細胞が弱いと環境の変化に対応できず、果物が割れてしまいます。
環境の変化は必ずあるので、それを前提に人間がどうサポートできるかを考えました。
肥料をいくらこだわっても、木の根がしっかりと張っていないと、いくら良い肥料を与えても強い果物はできません。
しっかりと根を張らせるためには、雑草が大事です。雑草をある程度生えさせることで、土の乾燥を防いで台風でも割れることなく、密度の濃い果物を作れています。
土にとって最も良くないのは乾燥です。雑草がないと土に直射日光が当たり土が固くなってしまいます。
草を生えさせたほうが、養分を少し吸ってしまうかもしれませんが、それ以上に乾燥を防ぎ、土の柔らかさを保ってくれます。
水分の多い土には、たくさんの微生物が働きやすくなります。そのおかげで木の根が張りやすくなります。根がしっかりと張ると、肥料を吸収しやすくなり味の濃い果物ができます。
<うちやま農園のデコポン>
農家の中でも果樹農家は、かなりハードルが高いと思います。一番の近道は、自分で果物を食べておいしいと感じた果樹園に修行に行くことです。
修業先で頑張れたら、自分の畑を持てるように、いろいろなつながりを紹介してもらえることもあります。もちろんタイミングがありますので、絶対とは言えませんが。
ひとりで0から農業を立ち上げることは、とても大変です。すでにうまくできている知識ややり方を習うほうが早いですね。
畑も初めから自分で作るのではなく、農家をやめるところを見つけて、引き継がせてもらうのが早いと思います。
農業には、国や自治体などの補助金も利用できるので、情報を調べてから取り組むことをおすすめします。
大事なのは、人とのつながりです。そして、本当においしい果物を作ろうと真剣に取り組むことです。弟子入りするときは、どういった姿勢で果物を作っている農家なのかを見極めることが重要です。
「うちの果物が一番」と言って、新しい試みをせず、やり方に固執してしまうと発展はできません。果物だけでなく、他の農家でも良いアイデアを持っていたら取り入れる柔軟性があると良いですね。
遠回りに感じるかもしれませんが、果物が実るのに時間がかかるのと同じで、事業も長い目で見て本質を追求することが必要だと思います。
果樹園は親から引き継ぐことが多いかと思いますが、私の場合は親との関係を良好に保つことが難しかったですね。折り合いがつかず、独立する人たちもいます。
早くから経営者目線で考えられるようになるので、それでも良いかもしれません。知識や経験の不足により、大変なことも多いと思います。
親と一緒に経営することで親に頼ってしまい、経営者としての自覚を持てないこともあります。
私が選んだのは、親と一緒に果樹園を育てていく道です親との関係を良好に保ちつつ、新しいやり方を取り入れていくときにはやはり摩擦がありました。時間をかけてすり合わせていく、忍耐力が必要でした。
あとは、他人の意見をどう取り入れていくかも難しいポイントです。農業をやると、いろいろな人がさまざまな意見をくれると思いますが、私はいつも人の意見よりも果物を見ています。
果物がおいしいかどうかが、全ての判断基準です。もちろん、いただいたアドバイスは取り入れてみますが、盲目的に信じるのではなく自分で試してから判断します。
20代のころは、人から教えてもらうことが嫌で意地を張っていました。でも、すでにおいしい果物を作っている農家から教えてもらったほうが、最初から答えに近づけて効率が良いのです。
子どもが生まれ、もっと稼がなければと思ったときですね。アルバイトと家業の手伝いで、人に会う機会がありませんでした。
これではだめだと思って、自分で食べておいしいと思った柿の生産者さんに弟子入りして観察させていただいたり、経営セミナーに参加したりしました。
外に出たこと、会う人を変えたことが、私にとっては考え方が変わったきっかけです。
農園の運営だけではなく、古民家を活用してうちやま果樹園で作った果物を加工して提供することです。
自分の果樹園だけでなく、農業を通して地元、地域を盛り上げるような活動もしていきたいと思います。
きっかけは、地元の小学校が廃校になったことでした。さみしくなり、もっと活気あふれる街並みを取り戻したい思いに駆られ、気づいたら町興しの活動団体の副会長に立候補していました。
昔はこんなに活動的な人間ではなかったのですが、子どもたちに元気な町を残したいと思うようになり行動しています。自分ができる果物作りを通して、貢献していきたいと考えています。
自分次第で何でもできます。自分のやりたいことを言葉にすることが大事です。
私の場合も「こんなことがやりたい」と数年前に妻や友人に話していたことが、今ほとんど現実になっています。
言葉にして発信することが、実現するための1歩目だと思うので、独立したい気持ちをぜひ発信してください。自分にウソをつかず、楽しんでいたら協力してくれる人が集まってきます。起業は大変ですがやりがいもあります。頑張ってください。
「DokTech」取材担当者より
インタビューでは奥様と一緒に思い出を紐解くようにお話しいただきました。柔らかな雰囲気のインタビューのなかで、外から雨音がすると両名、すぐに仕事人のお顔に。ご夫婦の愛情を感じる一場面でした。うちやまさん、ありがとうございました。これからますますのご活躍を応援しています。
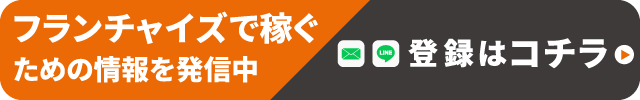
 DokTech編集部 独立・起業の最新ニュースや、明日からすぐ使えるテクニックを、分かりやすくご紹介!
DokTech編集部 独立・起業の最新ニュースや、明日からすぐ使えるテクニックを、分かりやすくご紹介!
フランチャイズ経営者やフリーランス、法人役員など、多種多様なキャリアをもつメンバーでお届けしています。